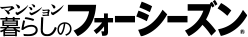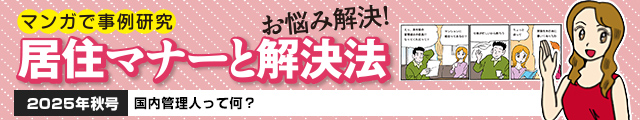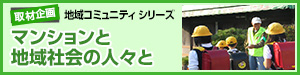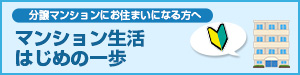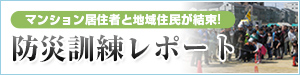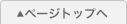- 連載
- マンガで事例研究
- 2025.10.01掲載
●なぜ、国内管理人制度を創設?
こうした状況に対して、海外にいる区分所有者に代わって連絡相手などとして、国内代理人等を指定することを規約で定めている管理組合も既にあります。しかし、実態として以下のような課題がありました。
●誰が国内代理人であるのか、管理組合に届け出がない。
●管理組合は、国内代理人がどんな権限をもっているのかわからない。
●1つのマンション内でも国内管理人が住戸ごとに異なる権限になっていることがあり、管理組合として取り扱いが難しい。
●1つのマンションで、複数の住戸が同じ代理人に委任しており、1人の人が多くの議決権を行使できる。民主的な運営が阻害される可能性がある。
●国内代理人制度がマンション売買時の重要事項説明に規定されていても、中古購入者に承継されるのかが明確でない。
こうした問題があり、区分所有法改正で国内管理人制度が生まれました。規約で規定すれば、マンションで海外に居住する区分所有者に代わって、連絡先となる国内管理人を置くことが義務化されます。
●国内管理人って何をする人?
国内管理人の届け出により、管理組合は国内管理人に総会開催案内の連絡などを行います。国内管理人は、総会での議決権の行使、管理費などの支払いなどを行います(新版 区分所有法 第6条の2(国内管理人)【改正法(令和8年4月施行)新法】)。マンションによっては新たに役割を付加できますが、法律で決められた役割を減らすことはできません。
どのような場合に必ず国内管理人を選んでもらうのか。それは、マンションごとに規約で規定することができます(例えば、1年以上日本から不在になる場合、日本語を解さない場合など)。
規約で規定され、マンションで国内管理人制度が導入されると、区分所有者は管理組合に国内管理人を届け出ることになります。管理組合は、国内管理人に連絡します。管理費等の引き落としの口座を、国内管理人に開設してもらうことも可能です。
国内管理人は、同じマンション内では、基本的には同じ権限になります。この制度は、規約で明記すれば当然、中古購入者にも承継されます。
管理組合の役員にも就任してもらいたい場合は、規約で役員に就任できる資格に規定しておくことになります。
また、同じマンション内で、同じ国内管理人に権限が集中しないようにする配慮も必要です。また、どのような人が望ましいのか。管理組合内で話し合い、資格を制限することもできます。
第六条の二 区分所有者は、国内に住所又は居所(法人にあっては、本店又は主たる事務所。以下この項及び第三項において同じ。)を有せず、又は有しないこととなる場合には、その専有部分及び共用部分の管理に関する事務を行わせるため、国内に住所又は居所を有する者のうちから管理人を選任することができる。
2 前項の規定により選任された管理人(次項及び第四項において「国内管理人」という。)は、次に掲げる行為をする権限を有する。
二 専有部分の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為
三 集会の招集の通知の受領
四 集会における議決権の行使
五 共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して負う債務又は規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して負う債務の弁済
4 区分所有者と国内管理人との関係は、第二項に定めるもののほか、委任に関する規定に従う。
●最後に
管理組合運営に新しい制度ができます。その基本は、どんな区分所有者も管理組合の構成員として、「建物並びにその敷地及び附属施設の管理が適正かつ円滑に行われるよう、相互に協力しなければならない。(新版 区分所有法 第5条の2(区分所有者の責務)【改正法(令和8年4月施行)新設】)」ということです。そのうえで、自ら執行が難しい場合に、代わりの人を選定しましょうということになります。国内管理人を選定したからといって、区分所有者の責務がなくなるわけではないので、どこにいても区分所有者はマンション管理に関心を持ち、責任を持ちましょう。これがマンションを所有することに伴う大事な責務です。
参考文献
齊藤広子 他:マンションの所有者のグローバル化 マンション学65号 p.23-29 2020年
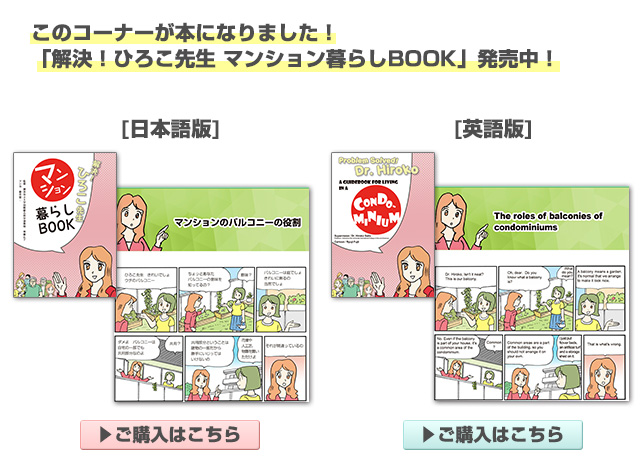
 Profile
Profile齊藤 広子
横浜市立大学国際教養学部不動産マネジメント論担当教授。工学博士、学術博士、不動産学博士。
著書に『新・マンション管理の実務と法律』(共著・日本加除出版)、『不動産学部で学ぶマンション管理』(鹿島出版会)、『これから価値が上がる住宅地』(学芸出版社)、『初めて学ぶ不動産学』(市ヶ谷出版)、『住環境マネジメント〜住宅地の価値をつくる〜』(学芸出版社)など多数。