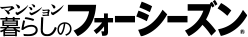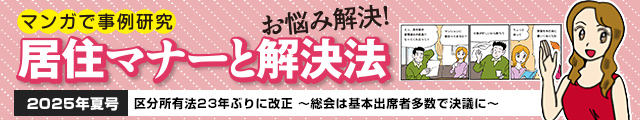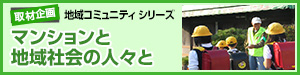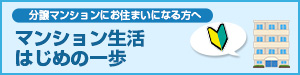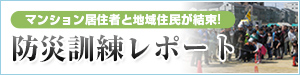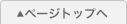- 連載
- マンガで事例研究
- 2025.07.01掲載
え? いつ決まったんだろう……。「総会で決まりました」って、最近総会があったのかな。
いつもなら、「齊藤さん、総会の議案書をお渡ししましたが、ご出席できない場合は、委任状か議決権行使書を出してくださいね」って、厳しく催促されるのに。
このごろ、マンションの大事なことがいつ決まっているのか、まったく見えない気がする。こわいな……。
●はじめに ─区分所有法とは?─
23年ぶりに区分所有法が改正されます。区分所有法?? それって何?という方もいるかもしれません。確かに、毎日の暮らしで、この法律を感じることはないかもしれませんね。私たちが暮らしているマンションは、1つの建物なのに区分して所有し、1つの建物に所有者がたくさんいることになります。そうなりますと、民法の大原則である、1つのものに同じ権利は1つという、一物一権主義に反するので、区分所有法という特別な法律ができています。この法律が生まれたのは、1962年(昭和37年)になります。その後、1983年(昭和58年)、2002年(平成14年)と大改正をし、今回2025年(令和7年)にまた大きな改正を行いました。
その背景には、マンションの2つの老いの問題があります。マンションの老朽化が進み、それを管理する人も老い、そのなかでどのように管理を進めていくのか。そのために、区分所有者間の権利の調整、管理のルールを定めた区分所有法、そしてマンションの管理を支える体制を整えたマンション管理適正化法、マンションの再生の事業を支えるマンション再生法、被災時のマンションの復旧・再生を支える被災マンション法、再生に関する融資メニューが増えることから住宅金融支援機構法も改正されました。
●区分所有法等の改正のポイント
改正のポイントはいくつかあります。ここでは簡単に、管理に関して主要なポイントを説明します。
1.区分所有者の責務が位置づけられます。
2.マンションが多様化し、人も建物も老いてきているのに、それに対応した新たな管理体制がありませんでした。そこで、所在等不明の所有者を裁判所が認めた場合に、集会決議から除外する仕組みや、出席者多数で決議をする仕組みができます。
3.国外の区分所有者には、国内管理人を選んでくださいという制度も用意されます。所有権のグローバル化は確実に進み、運営上の課題が多くありました。この国内管理人により、総会の委任状の回収などがしやすくなる等が期待されています。
4.築年数の経ったマンションでは、共用部分だけでなく、専有部分の給排水管などの取り換えも管理組合に一緒にやってほしいという、区分所有者の需要が高まっていましたが、管理規約で明記すれば、専有部分の給排水管などの取り換えを管理組合が行うことが可能となります。すでに標準管理規約では対応済みでしたが、マンション全体を合理的に効率的に総合的に管理しやすくするためです。
5.役員のなり手不足から、管理者を第三者にお願いすること、特に管理業者にお願いすることがだんだん増えてきています。管理者はそのマンションの管理の最高責任者になり、実質的には多くの権限を持っています。そこで、区分所有者の中から管理者を選ぶわけではないので、区分所有者から見れば、「自分たちの意見がちゃんと反映されるだろうか」「大規模修繕等を勝手に発注しないだろうか、特に管理業者の関係の会社などに・・・」という不安・懸念がありました。そこで、管理業者管理者方式の導入の際には、国がすでに示しているガイドラインなどを参考とし、管理業者の説明を聞き、区分所有者自身が判断できる説明会を開催し、大事な工事の発注も、管理業者およびその関係者が関与する場合には、説明会の開催を行うことが法律で規定されます(マンション管理適正化法)。
6.管理費を滞納している住戸があり、新しく買ってくれる買主が決まらない場合に、管理組合で買い取りたいという需要が一定数あります。従来は「でも、管理組合がそんなことできるの?」と、法的に可能かどうか不明確でしたが、 管理組合法人が区分所有権・土地を取得できることが法で明確になります。